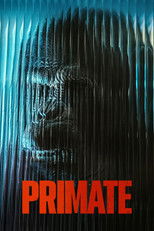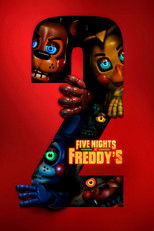札幌・シアターキノで行われた映画『遠い山なみの光』の上映後ティーチインに、石川慶監督が登壇。観客からの質問に答えながら、石川監督は、時代を超える物語を“いま”の観客へ届けるための工夫や、俳優とのやり取りを率直に語りました。その様子をレポートします。
■『遠い山なみの光』のあらすじ
日本人の母と英国人の父を持つニキ(カミラ・アイコ)が、母・悦子(吉田羊)の人生を題材に物語を書こうとするところから始まります。戦後、長崎から渡英し、長女を自死で失った母は長く沈黙してきた過去を語り始める。1952年、復興期の長崎で若き日の悦子(広瀬すず)は、佐知子(二階堂ふみ)と幼い娘・万里子(鈴木碧桜)と出会い、彼女たちと過ごしたひと夏の記憶を胸に刻む。やがてニキは、母の語りに潜む〈嘘〉に気づいていく──。
試写会レビュー記事もチェック!
嘘に隠された願い──戦後、ひと夏の記憶が胸を打つカズオ・イシグロ×石川慶『遠い山なみの光』
「80年代は時代劇」!? 忠実な再現より観客と時代をつなぐ“感覚”

(C)2025 A Pale View of Hills Film Partners
また、近年の映画に多いポリティカル・コレクトネスの流れについてもふれ、「大事な視点だと思う一方で、それだけに収まらない深さがある」と原作の魅力を強調。登場人物の選択には犠牲や矛盾が含まれており、その“グレー”な部分こそが観客に響くと語りました。
衣装や美術は当時の資料を参考にしつつ、色彩や方言には“いま”の感覚を加えています。昔の日本映画の空気をリスペクトしながらも、模倣ではなく再解釈を選んだ点も印象的です。
俳優たちと作り上げた人物像──役の“記憶”を埋める俳優たちの真摯
吉田羊さんが演じた悦子のあるクライマックスシーンは、彼女にとって本作で初めて撮影するシーンだったことを明かし、吉田さんは複雑な感情を即座に体現したというエピソードを披露してくれました。監督は「無茶振りだった」と苦笑しつつも、その表現力に大きな信頼を寄せたといいます。
さらに、二郎を演じた松下洸平さんには監督が3ページにわたる“履歴書”を手渡しました。家庭環境や職業観まで緻密に描かれた設定をもとに、松下さんは「戦後の猛烈社員」にとどまらない人物像を形作ったといいます。

(C)2025 A Pale View of Hills Film Partners
小説の余白に、映画ならではの答えを──原作との“解釈”の違い

(C)2025 A Pale View of Hills Film Partners
映画化にあたっては、ニキの視点を物語の軸に据えた結果、「発見したことを提示しないのは映像作品として不誠実に映ってしまう」と考え、原作で曖昧にされていた部分にひとつの解釈を与えることを決断。
この解釈は独断ではなく、脚本段階でカズオ・イシグロ本人に相談し了承を得ています。石川監督は「もちろん異論もあるだろうけれど、映画として提示するならこの形しかないと覚悟した」と振り返りました。原作の余白を尊重しながらも、映画ならではの答えを提示したことが、本作の大きな特徴となっています。
“記憶”に宿るものを伝えるために──戦後80年に残すべき物語
「正確な“記録”だけでは届かないものがある。人の“記憶”にこそ伝わるものがある。だからこそ今、残さなければならない」
戦後80年が過ぎ、体験者の声が失われつつあるいまこそ描くべき物語だと、石川監督は強調しました。


観客との熱を帯びたやり取りを経て、石川監督の言葉は作品そのものの厚みをいっそう際立たせたように感じます。そして振り返れば、本作が目指したのは「正確な記録」ではなく「揺らぎを抱えた記憶」を映すこと。
その姿勢は、体験者の声が失われつつある今を生きる私たちにとっても、大切な問いかけとなっています。
まさにタイトルの通り――記録ではなく記憶を映す。
その姿勢は、スクリーンの向こうでしか味わえない体験として観客に届きます。
この記事を通じて感じ取った想いを、ぜひ映画館で自分自身の“記憶”として刻んでほしいと思います。
「80年代は時代劇」!? 忠実な再現より観客と時代をつなぐ“感覚”

(C)2025 A Pale View of Hills Film Partners
また、近年の映画に多いポリティカル・コレクトネスの流れについてもふれ、「大事な視点だと思う一方で、それだけに収まらない深さがある」と原作の魅力を強調。登場人物の選択には犠牲や矛盾が含まれており、その“グレー”な部分こそが観客に響くと語りました。
衣装や美術は当時の資料を参考にしつつ、色彩や方言には“いま”の感覚を加えています。昔の日本映画の空気をリスペクトしながらも、模倣ではなく再解釈を選んだ点も印象的です。
俳優たちと作り上げた人物像──役の“記憶”を埋める俳優たちの真摯

(C)2025 A Pale View of Hills Film Partners
吉田羊さんが演じた悦子のあるクライマックスシーンは、彼女にとって本作で初めて撮影するシーンだったことを明かし、吉田さんは複雑な感情を即座に体現したというエピソードを披露してくれました。監督は「無茶振りだった」と苦笑しつつも、その表現力に大きな信頼を寄せたといいます。
さらに、二郎を演じた松下洸平さんには監督が3ページにわたる“履歴書”を手渡しました。家庭環境や職業観まで緻密に描かれた設定をもとに、松下さんは「戦後の猛烈社員」にとどまらない人物像を形作ったといいます。
小説の余白に、映画ならではの答えを──原作との“解釈”の違い

(C)2025 A Pale View of Hills Film Partners
映画化にあたっては、ニキの視点を物語の軸に据えた結果、「発見したことを提示しないのは映像作品として不誠実に映ってしまう」と考え、原作で曖昧にされていた部分にひとつの解釈を与えることを決断。
この解釈は独断ではなく、脚本段階でカズオ・イシグロ本人に相談し了承を得ています。石川監督は「もちろん異論もあるだろうけれど、映画として提示するならこの形しかないと覚悟した」と振り返りました。原作の余白を尊重しながらも、映画ならではの答えを提示したことが、本作の大きな特徴となっています。
“記憶”に宿るものを伝えるために──戦後80年に残すべき物語

「正確な“記録”だけでは届かないものがある。人の“記憶”にこそ伝わるものがある。だからこそ今、残さなければならない」
戦後80年が過ぎ、体験者の声が失われつつあるいまこそ描くべき物語だと、石川監督は強調しました。

観客との熱を帯びたやり取りを経て、石川監督の言葉は作品そのものの厚みをいっそう際立たせたように感じます。そして振り返れば、本作が目指したのは「正確な記録」ではなく「揺らぎを抱えた記憶」を映すこと。
その姿勢は、体験者の声が失われつつある今を生きる私たちにとっても、大切な問いかけとなっています。
まさにタイトルの通り――記録ではなく記憶を映す。
その姿勢は、スクリーンの向こうでしか味わえない体験として観客に届きます。
この記事を通じて感じ取った想いを、ぜひ映画館で自分自身の“記憶”として刻んでほしいと思います。
早川真澄
ライター・編集者
北海道の情報誌の編集者として勤務し映画や観光、人材など地域密着の幅広いジャンルの制作を手掛ける。現在は編集プロダクションを運営し雑誌、webなど媒体を問わず企画制作を行っています。

 注目映画一覧
注目映画一覧