歌舞伎の新たな表現領域に挑む「歌舞伎NEXT」シリーズ。その第2弾として上演された「歌舞伎NEXT 朧の森に棲む鬼」は、シェイクスピアの名作「リチャード三世」に着想を得た、嘘と欲望に支配された男の転落と野望を描く作品です。
2024年11月から12月に新橋演舞場、2025年2月に博多座で上演され、主人公・ライとサダミツを松本幸四郎さんと尾上松也さんがWキャストで演じました。シネマ歌舞伎としては、幸四郎版が2026年1月2日(金)、松也版が1月23日(金)から全国公開されます。
公開に先駆け『歌舞伎NEXT 朧の森に棲む鬼(松也版)』で、主人公・ライ役を務めた尾上松也さんに、UHBアナウンサー・柴田平美がインタビュー。長年憧れてきた作品への思いや、役に向き合う覚悟について話を聞きました。
尾上松也さんインタビュー
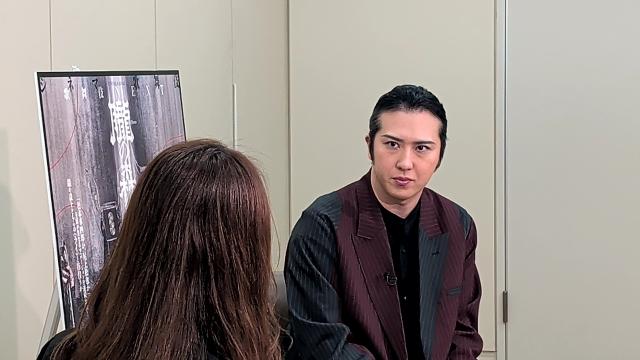
松也:率直に、とても嬉しかったです。初演時に主人公・ライを演じていた松本幸四郎(当時は市川染五郎)さんの舞台を拝見し、その圧倒的なかっこよさに強い憧れを抱いていました。まさかその後、自分が同じ作品に、しかも同じライ役で、幸四郎さんとWキャストとして立つことになるとは思ってもいませんでした。喜びと同時に、大きなプレッシャーと不安もありました。当時ライを演じていたご本人と同じ役に挑むわけですから、正直「まいったな…これは大変だぞ」と感じたのも事実です。以前から、この作品を歌舞伎NEXTで上演するという話を聞いていたので、その際には「キンタ役で参加できたら」と思っていました。ですから、ライ役のお話をいただいた時は、本当に驚きました。
―――主人公・ライは、とことんダークなヒーローだと感じました。松也さんご自身は、どのようにライを演じようと考えましたか。
松也: 正直に言うと、稽古の初めは自分でも方向性を定めきれず、手探りの状態でした。演出のいのうえひでのりさんが、どのように作品を立ち上げていくのかも、まだ見えていなかったからです。初演時の幸四郎さんのライの印象が強く残っていたため、その方向性で進むのだろうと考えていました。しかし実際には、幸四郎さんもいのうえさんも、前回の上演をまったく意識していなかったのです。「歌舞伎NEXTとして新しい作品をつくる」という姿勢で初日から臨まれているのを見て、「もう過去を気にする必要はない」と気持ちを切り替え、自分なりのライを突き詰めていこうと思いました。幸四郎さんを意識して演じ分けたつもりはありませんが、結果的にはまったく異なるタイプのライになったと感じています。私の中でライは、簡単に言えば“普通の人間が悪に取り込まれて、抗えずに敗北していく物語”の主人公です。観客の皆さんに、もし何かひとつでも違う選択肢があれば、ライは鬼にならずに済んだのではないか、彼は本来、ごく普通の人間だったのではないかと感じてもらえたらという思いで演じていました。
松也: ライの行動は極悪非道ですが、その根底にある人間らしさだけは失わないよう、常に意識していました。もともと彼は、小悪党として物語が始まります。その性分が最後まで完全には消えなかったという部分を随所に感じてもらえたらと思って演じていました。特に大切にしていたのが、キンタとの関係性です。そこにある絆や友情、そして愛情のようなものは、私が演じるライの中で常に滲むようにしたいと考えていました。キンタ役の尾上右近くんとは普段から交流があり、その関係性が舞台にも表れていた部分があったと思います。意識的に幸四郎さんと差別化しようとしたわけではありませんが、結果として違いが感じられるポイントのひとつになったのではないでしょうか。長年一緒に作品を作ってきていますので、言葉を交わさなくても通じる部分が多かったと思います。実際に芝居が始まれば、相手の反応を受け取りながら自然にやり取りが生まれていきました。キンタに関しては、普段から築いてきた関係性が、非常に大きな助けになったと感じています。
―――古典演目と“歌舞伎NEXT”の作品とで、舞台に立つ際に意識している違いはありますか?
松也: あまり大きな意識の違いはありません。『朧の森に棲む鬼』は劇団☆新感線の作品ですので、一般的にイメージされる七五調の、いわゆる歌舞伎らしい台詞回しは多くありません。ただ、歌舞伎の古典演目であってもすべてがそうした台詞回しというわけではなく、現代演劇に近い自然な語り口で進む芝居も数多くあります。そう考えると、“歌舞伎NEXT”や新作だからといってあまり意識を変えているわけではありません。歌舞伎という表現の中には、もともとさまざまなジャンルや台詞のスタイルが存在しており、そこに感情を込めて役を演じるという作業なので、古典演目と比べて、演じる上での意識が大きく変わることはありませんでした。


松也:それもひとつの理由だと思います。ただ、基本的には歌舞伎に限らず、演劇全般に共通する部分だと感じています。ミュージカルや映画であっても、役を通して台詞に感情を込めていくという作業の本質は同じです。そのため、どのジャンルに取り組んでいても、根本にある意識が大きく変わることはありません。変わるのは表現の方法やテクニックの部分で、その都度表現手段を切り替えているという感覚に近いですね。
―――上演時間は3時間を超え、激しい殺陣も多い作品でした。相当なエネルギーを要したのではと感じましたが、体力や喉のコンディションはどのように保っていたのでしょうか。
松也: 正直に言って、毎回体力的には限界に近い状態でした。休憩を含めると上演時間は約4時間に及びますし、ライは登場回数も多く、同じ状態で舞台に出る場面がほとんどありません。登場のたびに化粧や衣裳が変わり、一幕と二幕の間でも化粧替えを行うため、準備が終わるとすぐに次の幕が始まるという状況でした。舞台上では常に全力で芝居と立廻りに向き合い、舞台裏では走り続ける。まさにノンストップで最後まで駆け抜ける感覚でした。これまで経験してきた作品の中でも、体力的な厳しさという点では、おそらく最も過酷な舞台だったと思います。
―――殺陣やアクションシーンの多さも、体力的な負担を大きくしていたのではないでしょうか。
松也: 特に後半、ライが将軍となってからは殺陣が連続し、ひとりで複数の相手と対峙する場面も多くて余計に疲れるんです(笑)。本作では、歌舞伎の立廻りに加え、アクション指導を担当した川原さんによる劇団☆新感線ならではの立廻りを織り交ぜています。そのため、普段とは異なる身体の使い方が求められ、疲労の質もまったく違うものになりました。そこに早替えが重なることで、初めて舞台稽古を行った際は、「これは最後までもたないな」と感じたほどです。2か月の公演期間を乗り切れるのか不安になるほど厳しい舞台でした。
松也:息抜きをするような時間は、ほとんどありませんでした。公演前は毎回、「これから4時間のマラソンが始まる」というような気持ちでした。ただ、いざ幕が上がると、作品そのものの力や、ライという役の持つ魅力に自然と背中を押されていました。非常に演じがいのある役でもあり、舞台が進むにつれてエネルギーをもらう感覚がありました。次第に気持ちが高まり、アドレナリンが出てくるような状態になっていったと思います。終演後には、「またすぐにやりたい」と感じるほどの充実感もありましたし、客席から伝わってくるお客様の真剣なまなざしや熱気も大きな支えでした。作品の力と観客の思い、その2つに助けられて、最後まで走り切ることができたのだと思います。
―――舞台全体から凄まじいエネルギーを感じましたが、森や滝といった大掛かりな舞台装置も印象的でした。演じる側としては、相当大変だったのではないでしょうか。
松也:終盤の水を使った立廻りは、まさに体力が尽きる寸前の状態でした。場面としても、ライの命が尽きる直前の「死闘」にあたりますので、その切迫感は非常にリアルだったと思います。実際、私たち自身も体力の限界が迫る中での大立廻りで、そこに水の演出が加わることで、さらに過酷な状況になっていました。立廻りが終わると、間髪入れずに衣裳を替え、花道へ飛び出して退場します。その後すぐに化粧を直し、カーテンコールに戻るという、まさに怒涛の展開でした。あの場面に関しては、意識的に気持ちを作らなくても、自然とクライマックスへと向かう境地に到達していたように感じています。体力的には本当に厳しかったですが、その過酷さも含めて、改めて非常によく練り込まれた作品だと実感しました。


松也:舞台に立つ上で、映画として撮られることを意識することはまったくありませんでした。私たちは、あくまで劇場でお客様に向けて、いつも通り全力で芝居をすることを最優先にしていました。むしろ、映像を撮っているという意識を持ってしまうと、感覚やスケールが変わってしまう恐れがあります。劇場で生まれている熱気や集中力を、そのまま映画として受け取ってもらうためにも、特別なことはせず、舞台の芝居として何かを変えることはありませんでした。
―――今後、松也さんが映像作品として挑戦してみたい歌舞伎演目や、新たな表現の構想はありますか。
松也:挑戦してみたい作品や、形にしてみたい表現は、まだまだ数多くあります。ただ、歌舞伎NEXT第2弾となった「朧の森に棲む鬼」は、非常に挑戦的で、なおかつ進化を感じる作品でした。ぜひ、この流れを今後も続けてほしいと強く思っています。私自身も、また参加できるように、さらに力をつけていきたいと感じました。シネマ歌舞伎として映像化されることで、舞台で観るのとは異なる迫力や魅力が、存分に引き出されています。舞台と映像をつなぐ架け橋として、その可能性の広がりを強く実感しました。今回は演じている最中に「シネマ歌舞伎版」を意識することはありませんでしたが、逆に言えば、最初から“シネマ歌舞伎ありき”で表現を組み立てる、100%映像に振り切った作品があっても、面白いのではないかと感じています。
シネマ歌舞伎『歌舞伎NEXT 朧の森に棲む鬼』作品情報
作:中島かずき
演出:いのうえひでのり
製作・配給:松竹
出演:松本幸四郎、尾上松也、中村時蔵、坂東新悟、尾上右近、市川染五郎、澤村宗之助、大谷廣太郎、市川猿弥、片岡亀蔵、坂東彌十郎 ほか
収録公演:令和6年11,12月新橋演舞場公演

(C)松竹株式会社
尾上松也さんインタビュー
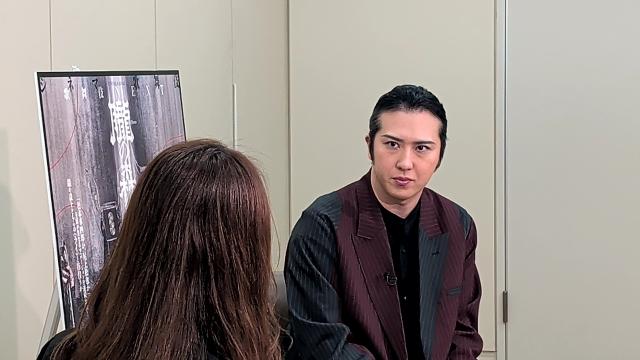
松也:率直に、とても嬉しかったです。初演時に主人公・ライを演じていた松本幸四郎(当時は市川染五郎)さんの舞台を拝見し、その圧倒的なかっこよさに強い憧れを抱いていました。まさかその後、自分が同じ作品に、しかも同じライ役で、幸四郎さんとWキャストとして立つことになるとは思ってもいませんでした。喜びと同時に、大きなプレッシャーと不安もありました。当時ライを演じていたご本人と同じ役に挑むわけですから、正直「まいったな…これは大変だぞ」と感じたのも事実です。以前から、この作品を歌舞伎NEXTで上演するという話を聞いていたので、その際には「キンタ役で参加できたら」と思っていました。ですから、ライ役のお話をいただいた時は、本当に驚きました。
―――主人公・ライは、とことんダークなヒーローだと感じました。松也さんご自身は、どのようにライを演じようと考えましたか。
松也: 正直に言うと、稽古の初めは自分でも方向性を定めきれず、手探りの状態でした。演出のいのうえひでのりさんが、どのように作品を立ち上げていくのかも、まだ見えていなかったからです。初演時の幸四郎さんのライの印象が強く残っていたため、その方向性で進むのだろうと考えていました。しかし実際には、幸四郎さんもいのうえさんも、前回の上演をまったく意識していなかったのです。「歌舞伎NEXTとして新しい作品をつくる」という姿勢で初日から臨まれているのを見て、「もう過去を気にする必要はない」と気持ちを切り替え、自分なりのライを突き詰めていこうと思いました。幸四郎さんを意識して演じ分けたつもりはありませんが、結果的にはまったく異なるタイプのライになったと感じています。私の中でライは、簡単に言えば“普通の人間が悪に取り込まれて、抗えずに敗北していく物語”の主人公です。観客の皆さんに、もし何かひとつでも違う選択肢があれば、ライは鬼にならずに済んだのではないか、彼は本来、ごく普通の人間だったのではないかと感じてもらえたらという思いで演じていました。

松也: ライの行動は極悪非道ですが、その根底にある人間らしさだけは失わないよう、常に意識していました。もともと彼は、小悪党として物語が始まります。その性分が最後まで完全には消えなかったという部分を随所に感じてもらえたらと思って演じていました。特に大切にしていたのが、キンタとの関係性です。そこにある絆や友情、そして愛情のようなものは、私が演じるライの中で常に滲むようにしたいと考えていました。キンタ役の尾上右近くんとは普段から交流があり、その関係性が舞台にも表れていた部分があったと思います。意識的に幸四郎さんと差別化しようとしたわけではありませんが、結果として違いが感じられるポイントのひとつになったのではないでしょうか。長年一緒に作品を作ってきていますので、言葉を交わさなくても通じる部分が多かったと思います。実際に芝居が始まれば、相手の反応を受け取りながら自然にやり取りが生まれていきました。キンタに関しては、普段から築いてきた関係性が、非常に大きな助けになったと感じています。
―――古典演目と“歌舞伎NEXT”の作品とで、舞台に立つ際に意識している違いはありますか?
松也: あまり大きな意識の違いはありません。『朧の森に棲む鬼』は劇団☆新感線の作品ですので、一般的にイメージされる七五調の、いわゆる歌舞伎らしい台詞回しは多くありません。ただ、歌舞伎の古典演目であってもすべてがそうした台詞回しというわけではなく、現代演劇に近い自然な語り口で進む芝居も数多くあります。そう考えると、“歌舞伎NEXT”や新作だからといってあまり意識を変えているわけではありません。歌舞伎という表現の中には、もともとさまざまなジャンルや台詞のスタイルが存在しており、そこに感情を込めて役を演じるという作業なので、古典演目と比べて、演じる上での意識が大きく変わることはありませんでした。

松也:それもひとつの理由だと思います。ただ、基本的には歌舞伎に限らず、演劇全般に共通する部分だと感じています。ミュージカルや映画であっても、役を通して台詞に感情を込めていくという作業の本質は同じです。そのため、どのジャンルに取り組んでいても、根本にある意識が大きく変わることはありません。変わるのは表現の方法やテクニックの部分で、その都度表現手段を切り替えているという感覚に近いですね。
―――上演時間は3時間を超え、激しい殺陣も多い作品でした。相当なエネルギーを要したのではと感じましたが、体力や喉のコンディションはどのように保っていたのでしょうか。
松也: 正直に言って、毎回体力的には限界に近い状態でした。休憩を含めると上演時間は約4時間に及びますし、ライは登場回数も多く、同じ状態で舞台に出る場面がほとんどありません。登場のたびに化粧や衣裳が変わり、一幕と二幕の間でも化粧替えを行うため、準備が終わるとすぐに次の幕が始まるという状況でした。舞台上では常に全力で芝居と立廻りに向き合い、舞台裏では走り続ける。まさにノンストップで最後まで駆け抜ける感覚でした。これまで経験してきた作品の中でも、体力的な厳しさという点では、おそらく最も過酷な舞台だったと思います。
―――殺陣やアクションシーンの多さも、体力的な負担を大きくしていたのではないでしょうか。
松也: 特に後半、ライが将軍となってからは殺陣が連続し、ひとりで複数の相手と対峙する場面も多くて余計に疲れるんです(笑)。本作では、歌舞伎の立廻りに加え、アクション指導を担当した川原さんによる劇団☆新感線ならではの立廻りを織り交ぜています。そのため、普段とは異なる身体の使い方が求められ、疲労の質もまったく違うものになりました。そこに早替えが重なることで、初めて舞台稽古を行った際は、「これは最後までもたないな」と感じたほどです。2か月の公演期間を乗り切れるのか不安になるほど厳しい舞台でした。

松也:息抜きをするような時間は、ほとんどありませんでした。公演前は毎回、「これから4時間のマラソンが始まる」というような気持ちでした。ただ、いざ幕が上がると、作品そのものの力や、ライという役の持つ魅力に自然と背中を押されていました。非常に演じがいのある役でもあり、舞台が進むにつれてエネルギーをもらう感覚がありました。次第に気持ちが高まり、アドレナリンが出てくるような状態になっていったと思います。終演後には、「またすぐにやりたい」と感じるほどの充実感もありましたし、客席から伝わってくるお客様の真剣なまなざしや熱気も大きな支えでした。作品の力と観客の思い、その2つに助けられて、最後まで走り切ることができたのだと思います。
―――舞台全体から凄まじいエネルギーを感じましたが、森や滝といった大掛かりな舞台装置も印象的でした。演じる側としては、相当大変だったのではないでしょうか。
松也:終盤の水を使った立廻りは、まさに体力が尽きる寸前の状態でした。場面としても、ライの命が尽きる直前の「死闘」にあたりますので、その切迫感は非常にリアルだったと思います。実際、私たち自身も体力の限界が迫る中での大立廻りで、そこに水の演出が加わることで、さらに過酷な状況になっていました。立廻りが終わると、間髪入れずに衣裳を替え、花道へ飛び出して退場します。その後すぐに化粧を直し、カーテンコールに戻るという、まさに怒涛の展開でした。あの場面に関しては、意識的に気持ちを作らなくても、自然とクライマックスへと向かう境地に到達していたように感じています。体力的には本当に厳しかったですが、その過酷さも含めて、改めて非常によく練り込まれた作品だと実感しました。

松也:舞台に立つ上で、映画として撮られることを意識することはまったくありませんでした。私たちは、あくまで劇場でお客様に向けて、いつも通り全力で芝居をすることを最優先にしていました。むしろ、映像を撮っているという意識を持ってしまうと、感覚やスケールが変わってしまう恐れがあります。劇場で生まれている熱気や集中力を、そのまま映画として受け取ってもらうためにも、特別なことはせず、舞台の芝居として何かを変えることはありませんでした。
―――今後、松也さんが映像作品として挑戦してみたい歌舞伎演目や、新たな表現の構想はありますか。
松也:挑戦してみたい作品や、形にしてみたい表現は、まだまだ数多くあります。ただ、歌舞伎NEXT第2弾となった「朧の森に棲む鬼」は、非常に挑戦的で、なおかつ進化を感じる作品でした。ぜひ、この流れを今後も続けてほしいと強く思っています。私自身も、また参加できるように、さらに力をつけていきたいと感じました。シネマ歌舞伎として映像化されることで、舞台で観るのとは異なる迫力や魅力が、存分に引き出されています。舞台と映像をつなぐ架け橋として、その可能性の広がりを強く実感しました。今回は演じている最中に「シネマ歌舞伎版」を意識することはありませんでしたが、逆に言えば、最初から“シネマ歌舞伎ありき”で表現を組み立てる、100%映像に振り切った作品があっても、面白いのではないかと感じています。
シネマ歌舞伎『歌舞伎NEXT 朧の森に棲む鬼』作品情報

(C)松竹株式会社
作:中島かずき
演出:いのうえひでのり
製作・配給:松竹
出演:松本幸四郎、尾上松也、中村時蔵、坂東新悟、尾上右近、市川染五郎、澤村宗之助、大谷廣太郎、市川猿弥、片岡亀蔵、坂東彌十郎 ほか
収録公演:令和6年11,12月新橋演舞場公演
柴田平美
UHBアナウンサー
UHBアナウンサー。ねむろ観光大使。土曜の情報番組「いっとこ!」の映画コーナーを担当。私が初めて観た映画は『名探偵コナン 天国へのカウントダウン』(2001)。故郷・根室に映画館がなかったため、観たい映画があると隣町の釧路まで行って観ていました。映画館では、一番後ろの真ん中で、ひとりで観るのが好き。ジャンルは、ラブ・ファンタジー・アクションを中心に、話題作をチェックしています。皆さんの心に残る映画を見つけるきっかけとなれますように。

 注目映画一覧
注目映画一覧









