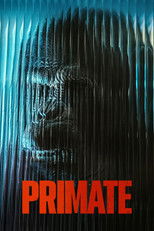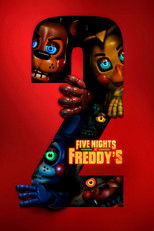毎週・木曜日の25:30から北海道・札幌のFM NORTH WAVE(JFL系)で放送されている、矢武企画制作・映画系トーク番組「キャプテン・ポップコーン」の内容をSASARU movieでも配信!
キャプテン・ポップコーンこと矢武企画・矢武兄輔が、映画の情報はもちろん、映画に関係するまちの情報、映画がもっと近くなる内容をお届けします。

この記事では9月11日(木)に放送した番組内容をお届けしています。 進行台本と放送内容を基に記事を作成しています。そのため、実際の放送内容とは違う表現・補足(話し言葉と書き言葉等)並びに、放送ではカットされた内容を含む場合がございます。 また、公開される映画館名や作品情報、イベントは上記日程の放送または収録時点のものになりますのでご留意ください。
【提供】キャプテン・ポップコーン/矢武企画
新作『宝島』に込めた思い──大友啓史監督インタビュー【前編】
大友:「知られていない歴史」に目を向けることが大切だと考えました。本土の方々も、沖縄戦についてはひめゆり学徒隊の話など戦争そのものは知っていても、その後のアメリカ統治下の沖縄については意外と知られていません。私自身もこの小説を読むまで、当時「戦果アギヤー」と呼ばれる若者たちの存在を知りませんでした。
彼らは食料も薬も足りない時代に、米軍の基地に忍び込んでそれらを盗み出し、庶民に分け与えていた。そうした行為がなければ、生き延びられない人も多かったのです。本土が高度経済成長に向かっていた時代に、沖縄ではこのような事実があったことは、あまり知られていません。

(C)真藤順丈/講談社 (C)2025「宝島」製作委員会

(C)真藤順丈/講談社 (C)2025「宝島」製作委員会
沖縄の基地問題は沖縄だけの課題ではなく、ガザやウクライナのような世界の紛争ともつながる問題だということを感じてもらいたいです。
大友:沖縄の人々はとても優しく、初対面の相手でも兄弟のように迎え入れてくれます。その優しさの根底には、困難な歴史をたくましく乗り越えてきた強さがあります。他者の悲しみや弱さを許容できる力も、そこから培われたものだと思います。
その優しさに甘えてはいけないと強く感じました。同じ日本人として、彼らの思いを共有し行動していくべきタイミングなのではないかと思います。映画制作が危機に直面した際も、「沖縄の人々が抱えてきた思いに比べれば、私たちの苦労など大したことはない」と自分に言い聞かせて進めました。

(C)真藤順丈/講談社 (C)2025「宝島」製作委員会

(C)真藤順丈/講談社 (C)2025「宝島」製作委員会
また、日常の中でアメリカ文化が入り込む様子も印象的でした。音楽などの演出も楽しく感じました。
大友:当時は基地の隣に街があり、米軍(在日米軍向け)のラジオ局「ファー・イースト・ネットワーク」から音楽が流れていました。現在の沖縄音楽文化の豊かさのルーツは、その時代にあります。また、沖縄のステーキ文化もアメリカとの関わりの中で育ちました。肉の処理の仕方が上手で、特別高価な肉ではなくても美味しく調理できる。その技術が根付いたからこそ、今日の沖縄ステーキ文化へと発展しました。
歴史には一面的な見方では捉えきれないものがあり、負の側面だけでなく、豊かな文化を生み出した側面もあります。歴史を単純に「正しい・間違い」と判断することはできません。私自身、この映画の製作を通じて、そのことを強く感じました。
※9月18日(木)の「キャプテン・ポップコーン」放送後に後篇のインタビュー内容を「SASARU movie」で配信予定です。
大友啓史監督プロフィール
1966年、岩手県生まれ。1990年にNHK に入局し、連続テレビ小説「ちゅらさん」シリーズ(01~07)や「ハゲタカ」(07)、NHK大河ドラマ「龍馬伝」(10)などの演出を担当。2009年『ハゲタカ』で映画監督デビューし、11年に独立。以降、『るろうに剣心』(12~21)シリーズや東映創立70周年記念作品『レジェンド&バタフライ』(23)などを手がける。最新作は9月19日(金)公開の映画『宝島』と、Netflixで12月配信予定の『10DANCE』。

映画『宝島』作品情報

(C)真藤順丈/講談社 (C)2025「宝島」製作委員会
1952 年のアメリカ統治下の沖縄を舞台に、米軍基地から物資を奪い、住民に分け与える「戦果アギヤー」と呼ばれる若者たちがいた。幼馴染のグスク、ヤマコ、レイ。そして、彼らの英雄的存在であり、リーダーのオンの4人だった。全てを懸けて、のぞんだある襲撃の夜、オンが「予定外の戦果」を手に入れ、突然消息を絶つ。残された3人はそれぞれ刑事、教師、ヤクザの道へ進むが、米軍支配と本土から見捨てられた環境の中、ある事件で感情が爆発。オンの失踪の謎と彼が持ち出した「何か」を追う中、米軍も動き出し、20年後の衝撃の真実が明らかに!
主演に妻夫木聡を迎え、広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太ら日本映画界を牽引する豪華俳優陣が集結!!第160回直木賞など三冠に輝いた真藤順丈による傑作小説「宝島」を企画から完成まで6年、2度の撮影延期などの困難を乗り越え、東映とソニー・ピクチャーズによる共同配給のもと実写映画化。

この記事では9月11日(木)に放送した番組内容をお届けしています。 進行台本と放送内容を基に記事を作成しています。そのため、実際の放送内容とは違う表現・補足(話し言葉と書き言葉等)並びに、放送ではカットされた内容を含む場合がございます。 また、公開される映画館名や作品情報、イベントは上記日程の放送または収録時点のものになりますのでご留意ください。
【提供】キャプテン・ポップコーン/矢武企画
新作『宝島』に込めた思い──大友啓史監督インタビュー【前編】

(C)真藤順丈/講談社 (C)2025「宝島」製作委員会
大友:「知られていない歴史」に目を向けることが大切だと考えました。本土の方々も、沖縄戦についてはひめゆり学徒隊の話など戦争そのものは知っていても、その後のアメリカ統治下の沖縄については意外と知られていません。私自身もこの小説を読むまで、当時「戦果アギヤー」と呼ばれる若者たちの存在を知りませんでした。
彼らは食料も薬も足りない時代に、米軍の基地に忍び込んでそれらを盗み出し、庶民に分け与えていた。そうした行為がなければ、生き延びられない人も多かったのです。本土が高度経済成長に向かっていた時代に、沖縄ではこのような事実があったことは、あまり知られていません。

(C)真藤順丈/講談社 (C)2025「宝島」製作委員会
沖縄の基地問題は沖縄だけの課題ではなく、ガザやウクライナのような世界の紛争ともつながる問題だということを感じてもらいたいです。

(C)真藤順丈/講談社 (C)2025「宝島」製作委員会
大友:沖縄の人々はとても優しく、初対面の相手でも兄弟のように迎え入れてくれます。その優しさの根底には、困難な歴史をたくましく乗り越えてきた強さがあります。他者の悲しみや弱さを許容できる力も、そこから培われたものだと思います。
その優しさに甘えてはいけないと強く感じました。同じ日本人として、彼らの思いを共有し行動していくべきタイミングなのではないかと思います。映画制作が危機に直面した際も、「沖縄の人々が抱えてきた思いに比べれば、私たちの苦労など大したことはない」と自分に言い聞かせて進めました。

(C)真藤順丈/講談社 (C)2025「宝島」製作委員会
また、日常の中でアメリカ文化が入り込む様子も印象的でした。音楽などの演出も楽しく感じました。
大友:当時は基地の隣に街があり、米軍(在日米軍向け)のラジオ局「ファー・イースト・ネットワーク」から音楽が流れていました。現在の沖縄音楽文化の豊かさのルーツは、その時代にあります。また、沖縄のステーキ文化もアメリカとの関わりの中で育ちました。肉の処理の仕方が上手で、特別高価な肉ではなくても美味しく調理できる。その技術が根付いたからこそ、今日の沖縄ステーキ文化へと発展しました。
歴史には一面的な見方では捉えきれないものがあり、負の側面だけでなく、豊かな文化を生み出した側面もあります。歴史を単純に「正しい・間違い」と判断することはできません。私自身、この映画の製作を通じて、そのことを強く感じました。
※9月18日(木)の「キャプテン・ポップコーン」放送後に後篇のインタビュー内容を「SASARU movie」で配信予定です。
大友啓史監督プロフィール

1966年、岩手県生まれ。1990年にNHK に入局し、連続テレビ小説「ちゅらさん」シリーズ(01~07)や「ハゲタカ」(07)、NHK大河ドラマ「龍馬伝」(10)などの演出を担当。2009年『ハゲタカ』で映画監督デビューし、11年に独立。以降、『るろうに剣心』(12~21)シリーズや東映創立70周年記念作品『レジェンド&バタフライ』(23)などを手がける。最新作は9月19日(金)公開の映画『宝島』と、Netflixで12月配信予定の『10DANCE』。
映画『宝島』作品情報

(C)真藤順丈/講談社 (C)2025「宝島」製作委員会
1952 年のアメリカ統治下の沖縄を舞台に、米軍基地から物資を奪い、住民に分け与える「戦果アギヤー」と呼ばれる若者たちがいた。幼馴染のグスク、ヤマコ、レイ。そして、彼らの英雄的存在であり、リーダーのオンの4人だった。全てを懸けて、のぞんだある襲撃の夜、オンが「予定外の戦果」を手に入れ、突然消息を絶つ。残された3人はそれぞれ刑事、教師、ヤクザの道へ進むが、米軍支配と本土から見捨てられた環境の中、ある事件で感情が爆発。オンの失踪の謎と彼が持ち出した「何か」を追う中、米軍も動き出し、20年後の衝撃の真実が明らかに!
主演に妻夫木聡を迎え、広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太ら日本映画界を牽引する豪華俳優陣が集結!!第160回直木賞など三冠に輝いた真藤順丈による傑作小説「宝島」を企画から完成まで6年、2度の撮影延期などの困難を乗り越え、東映とソニー・ピクチャーズによる共同配給のもと実写映画化。
キャプテン・ポップコーン
映画専門ラジオ番組
キャプテン・ポップコーンは、エフエムノースウェーブで毎週木曜日深夜1時半から放送するラジオ番組です。北海道・札幌で映画のお仕事に従事する「まちのえいが屋さん・矢武企画」が気になった映画の情報、映画に関係したまちの情報、そして、映画がもっと近くなるようなお話をお届けします。映画がはじける、映画で踊る夜、きょうも映画と、コミュニケーションしていきましょう!

 注目映画一覧
注目映画一覧